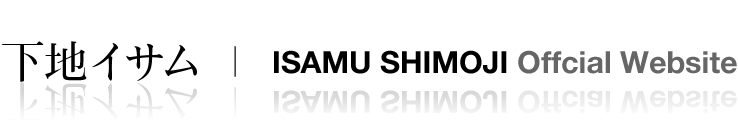影響論
ゆうべ寝る前に観たBSのドキュメンタリー番組の影響かな。
僕は、この「影響」というものについて深く考えないわけにはいかなくなってしまった。何やら空恐ろしいもののように思えて仕方がない。人間社会のここあそこに、至近距離のところにもたくさん転がっていて、自分がアンテナの周波数を合わせようと動きさえすれば、ただちに入り込んでくる。
世の中に善人と悪人の区別があるように、影響にも良い影響と悪い影響という、概念上の区別がある。そもそも影響を受けるということ自体どういう事なのだろうか、考えてみた。
たとえば音楽をやる人は、大抵誰か他の、音楽をやっている(やっていた)人の影響を少なからず受けていたりする。芸術家でも作家でも、卓球の選手でも将棋の棋士でも、誰かから、何かから、自分ではない他のものから影響を受けていることがあるはずだ。それは個人の自我から生まれ出てくるもの、純粋な気持ちや感情のようなものとは違って、その人から生まれ出ているように見えるけれど、外なる何ものかがあらゆる角度から入り込んでいて、元の存在を時に大きく揺るがせている。たとえば髭や体毛や細胞のように、その人だけのオリジナルのものとは違って、その人だけのもののように見えるというだけで、違うもの、料理に喩えると、素材に調味料を加えて、素材本来の味とは違う味になること。それが影響を受けるということなのかもしれない。
イギリスのある女性から生まれた可愛い男の子が、親の愛を一身に受けて成長したにもかかわらず、ある時から過激思想に染まり、テロリストになってしまう。母親は、何かの間違いだという思いを諦めることができない。幼い頃の我が子の写真を毎日見つめ、あの子がそんな人間になるはずはないと信じ続ける。きっといつの日か、あの頃のようにこの家に帰って来てくれると待ち続けている。ところが息子はどんどん過激思想に走り、大量殺人を犯すグループの一員になってしまう。
順調に育って来たと思われた彼が、殺人鬼に変貌してしまう要因が、宗教の思想(あるいは思想の偏った解釈)にあるとしたら、これはもう影響以外の何ものでもない。もともと持っていなかったものを外からのものによって持ってしまうということがそれだ。影響を受けやすい性格という素地があったにせよ、それは洗脳という外部からの変化要素に他ならない。他人を殺すことの正当性を、指導者やその集団組織の仲間たちから説かれ、受け入れているために、何一つ悪いことをしているという呵責が本人にはない。この変容ぶりは、どう考えても本性的なものではない。母親が無条件に子を愛する母性本能とは違って、理性の領域の中で塗り替えられたものだ。
いい影響と悪い影響のラインがどこからどこまでかはさておき、影響を受けてしまうという人間の理性というものに、ガラスのような弱さ、パンパンに空気の入った風船の皮一枚の危うさを感じて仕方がなかった。それが昨夜のドキュメンタリー番組を観たあとのやりきれない感想である。
こういう心持ちになってしまうと、いっそのことまったく他の何ものにも影響を受けない生き方がいいのではないかと思ってしまう。社会の中で生きている我々にとって、それはどだい無理な話なのかもしれない。影響を受けないという自己の強固な意志に頼る以外にない。どんな人生になるにせよ、何ものの影響をも受けないという生き方は、もしかしたら最も人間らしい生き方なのかもしれないとも思えてくる。自分の中にあるものをどこまで信じきれるか、ということが問われている。