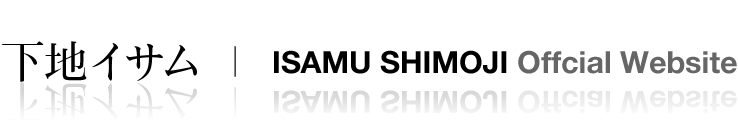ンタ・ピサ・フファイ
いやぁ~昨日は更新できずにごめんなさーい。
「小さな約束も必ず守る」
今年の目標に加えたいと思います。
では、「ンタ・ピサ・フファイ」の意味です。
むかしむかし、宮古島の野崎という村に三郎という男が住んでいました。
彼は農業をして暮らしていましたが、どうしようもない怠け者でした。
三郎は、農業が嫌いなわけではなかったのですが、村人たちが、どうしてこうもせっせせっせと毎日毎日、雨の日も風の日も、朝早くから日が暮れるまで畑に通い続けるのか、まったく理解できませんでした。そんなに毎日通ってまでする仕事というものが、畑にはあるのだろうか。それより自分には他にもっとやりたいことがある。家でゆっくり本も読みたい。たまには釣りにも行きたい。
畑仕事というものは、植え付けをして、時々肥料を撒いていれば、あとは収穫するだけでいいんじゃないのか。そう思いながら彼は、毎日まじめに畑に通う村人たちを、少しバカにした目で見ていました。
ところが、収穫時期になると、彼の作物は周りの畑の半分も収量がないのです。
たまたま今年だけそうなったのだと、認めたくない気持ちで強がってみたのですが、翌年もまたその翌年も結果は同じでした。
彼はますます理解に苦しむようになりました。土は同じだし、やっていることも大して変わらないはずだ...。畑に通い続けるということが何か意味があることなのか、そんなに大事なことなのか...。
彼は、解せない思いに駆られながら、ある日隣の家に住む収一兄さんに訊ねてみることにしました。ひとり暮らしの収一兄さんは、畑以外には何も興味が無いという感じで、毎日毎日朝から畑に出かけて行っては、晩まで黙々と働いて帰ってくるのです。村人たちも、彼のことは村一番の働き者だと褒め称えているほどです。
「兄さん、どうして毎日畑に通うのですか?」
三郎は、思っていることを率直にぶつけてみました。
「...」
収一兄さんは何も応えません。
この兄さんというのが、口数の少なさでも村一番と言われるほどの人なのです。どうしてそんなバカなことを訊くんだとでも言いたげな表情で、ただ黙々と耕運機のヘラをすげ替えています。
「毎日畑に通うことに何か意味があるんですかね?会社に勤めているわけでもないのに」
三郎も引き下がりません。
長い間沈黙があって、
「ンタピサフファイ」
収一兄さんがボソっと言いました。
「え!?今何て言いました?」
三郎がすっとんきょうな顔で訊きなおしました。
「ンタピサフファイよ」
「どういう意味ですか?」
「ンタ ピサ フファイ あとは自分で考えれ」
収一兄さんは投げやりにそう言うと、耕運機に乗って畑へと出かけていきました。
三郎は意味がわからない言葉に困惑し、少し拍子抜けしたのですが、その後も特に自分を変えることもないまま、相変わらず怠けた生活を続けていました。たまに畑に行っては肥料を撒いたり、気が向いた時だけは作物の葉っぱを間引きしたりする程度の作業しかしませんでした。
それから半年ほどが過ぎたある日、彼は村の小さな神事に参加することになりました。村人たちがたくさん集まっているウタキという場所で、神様に手を合わせながら、今年の豊作をお祈りするという行事です。三郎はなんら興味があるわけでもないので、一応お祈りするフリをして早く家に帰ることだけを考えていました。
すると、ガヤガヤと世間話をしている村人たちのところから「ンタピサフファイ」という言葉が突然三郎の耳に飛び込んできたのです。三郎は、確かに聞き覚えのあるこの言葉にひとりでに反応し、祈りをやめてその人たちのところに近寄っていきました。
「今、ンタピサフファイという言葉が聞こえてきたのですが、それはどういう意味ですか?」
一人だけ輪の外にいた村人に訊ねました。
「昔はよく使っていた言葉だけどね、今はもう使わなくなったさぁ」
と、その村人は感慨深げに話し始めました。
「ンタは方言で土のこと。ピサは足の裏、フファイとは肥料のことだよ。毎日畑に通う人は、ただ畑を見回るだけでも、自分の足で雑草を踏み潰して、その踏み潰された雑草が肥やしになって作物が育っていくわけさ。でも畑に行かない人は雑草に栄養分をとられて、作物が育ちにくいという意味だよ。つまり、何の意味も無いように見えることでも、それを積み重ねることで意味が生まれてくるし、継続することが大事ってことさ。小さなことをコツコツ続けることが大きな収穫につながっていくことの喩えだよ」
三郎はしばらくずっとその場を動けずにいました。
その言葉が、どこまでも自分の奥深くに浸み込んでいくような気がしました。
その日から三郎は変わりました。
毎日畑仕事に精を出す三郎がいました。