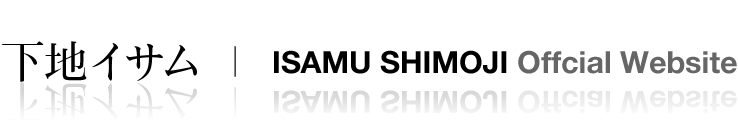旅の最後に...その2
皆さん、つづきが遅くなってすみません。
引っ張るつもりはなにもなかったんですが(笑)、急にバタバタしてしまいまして。
さぁ、つづきです。
前回の内容ですが、行きと帰りのルートが分かりにくかったですね。すみません。
そこだけ整理しておきます。
まず、どのようにグラナダまで行ったかと言いますと、
沖縄 → 成田 → ロンドン → リヴァプール → マドリード → グラナダ
そして帰りのルートは、
グラナダ → マドリード → ロンドン → 成田 → 沖縄
のはずでした。これで少しは見えてくると思います。
前回の話は、グラナダからの帰りの便マドリード行き、つまり一発目の飛行機が遅れている状況をお伝えしました。
<その2>
搭乗時刻になって初めて飛行機がいないことに気づいた僕らは、唖然としてその場に立ち尽くしていた。
出発予定時刻になってもアナウンスもなければ何の動きもない。
5分が過ぎ、10分が過ぎた。
出発予定時刻を10分ほど過ぎたとき、突然アナウンスがなり人々がまた行列を作った。
これはいったい...飛行機がないのにどうして並ぶのか?
しかも前の方を見ると、並んでいる人たちは次々にチケットを見せて中に入っていく。階段を下り、外に出てどんどん歩いていく。
彼らの行き先に目をやったとき、その答えがわかった。
遠く離れたところに、1機だけポツンと見えた。
模様の違う飛行機。
あんなのいたっけ?
どこかから借りてきたのだろうか?
あんなとこまで歩いていけというのか?
バスはないのか?
次々と疑問が頭をよぎりながらも、出発時刻を既に15分も過ぎていることにどうしても心が向いてしまって、とにかく急がなくてはと小走りになる。しかし急いでいるのは僕と上江洲さんぐらいで、他の乗客たちはまるでピクニックでも楽しむように、のんびりと、ときに大きな笑い声を上げたりしながら、ゆっくり飛行機に近づいていく。お年寄りの団体も多く、スローモーションのようにタラップを上がる。機内に荷物を収納するのにまた時間がかかる。
すべての客が座席につき、飛行機が動き出したのは、出発時刻から50分遅れてのことだった。さらに、僕と上江洲さんの席は、あろうことか最後尾だった。どこかに誰かの親切が入り込んだ形跡はまったくといって見られない。僕らのために何らかの特別な取り計らいがなされるような雰囲気もまったく感じられなかった。アウェイの地で不利な条件を突きつけられながら戦うスポーツ選手のように、いや、たとえそういう選手であっても、勝利への望みは決して捨てずに戦うはずだ。しかしこの時点で僕らの勝利への望みというのはすべて絶たれてしまったように思われた。
特に意味はないが、この飛行機のキャビンアテンダントはみんな男性だった。
そのCAの一人が僕と上江洲さんの座席のところにやって来て、
「ロンドンへお乗り継ぎのお客様ですね?」と、
スペイン訛りの英語で尋ねてきた。(それを待ってたよアミーゴ、スィー)
「そうです、そうなんですよ。こんなにも遅れていて1時間しか乗り継ぎ時間がないってのに大丈夫なんですか?」
そんなことを英語で喋れるはずもないが、僕らのおかれている精神状況と必死の形相から、おそらく言わんとするところが伝わったのだろう。
「ええ、大丈夫ですとも。あなたがたのような紳士を置いて行くはずがありませんよ。心配しないでください。ただし、飛行機が到着したら猛ダッシュで次の搭乗ゲートに向かってください」
笑みさえこぼしていたから、おそらくそのような事を言ったのだと思う。よし、勝利を信じよう。大丈夫のような気がしてきた。
グラナダを飛び立った飛行機は、1時間のフライトでマドリード空港に着いた。空にスピード違反がないんだったらぶっ飛ばしてほしかったのだが、遅れて飛んだ時間と同じ遅れで到着した。
(シートベルトのサインが消えたら勝負だ)
「思いっきり前に走るぞ、勇」
上江洲さんの目は、レコーディングのときのように真剣そのものだった。この目が「No Refuge」というアルバムを作り上げたのだ。「逃げ場がない!」って、この状況では皮肉以外のなんでもない。
ピンっ!
シートベルトサインが消えた。
「走るぞぉ」
乗客の間を掻き分けて走った。
必死に前に詰めより、掻き分け、そして進んだ。
しかし、そこまでだった。
飛行機の中央、翼の辺りで勢いはピタリと止まった。
大柄の外国人たちが大きな手荷物を下ろしたあとのその通路は、どんなにあがいても前になど進めるはずがなかった。
そのときだ。
「勇、座席に携帯電話を忘れてきたかもしれん。すまん、見てきてくれ」
(っえーっ!!マ、マ、マジでー!?)
僕よりも5~6人隔てて前にいる上江洲さんが、泣きそうな顔で後ろを振り向き、僕に言ったのだ。
(なんでこの場面でぇ...)
僕は意を決して振り向いた。
「エクスキューズミー、ソーリー、エクスキューズミー、ソーリー、エクスキューズミー、ソーリー」
何度繰り返したかわからない。
一人またひとりと、年老いたパッセンジャーたちのひんしゅくの眼差しの中を最後部の座席まで戻っていく。
オウンゴールとはこのことか。自ら敗北へ後戻りする切なさ。
サトウキビ畑を掻き分けて進むほうがまだスムーズだと思えるくらい、過酷な機内のイバンツガマ(狭道小)をちょとずつ猛進で突き進んでいく。
再びやっとたどり着いた後部座席に、
携帯電話はなかった。
シートの隙間も前のポケットも、しゃがみこんで下をのぞいてみても、それらしきものは見当たらない。
その場から一歩も前に進むことができずに、うなだれながら地獄のように長い時間が流れた。
つづく
ことを許して...