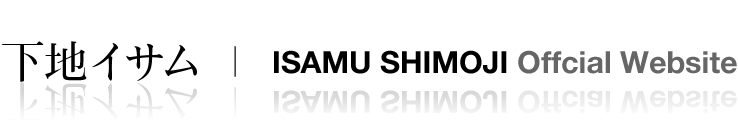ジョギング
その少年は、ある日急に思い立ったように走ってみることにした。
小さな島を一周する狭いアスファルトの道が、ずっと延びていって水平線に重なるところで見えなくなっているのを見ると、その先がどうなっているのか、何があるのか、自分の足で行って確かめてみたいという気持ちになった。
父の仕事の都合で沖縄本島からこの小さな島に移り住んでまだ一週間しか経っていない。島の中学校のみんなとはまだ馴染んでいるとまではいかないが、これからもっと仲良くなれそうな気はしている。
少年は、学校から帰るとすぐにジョギングができるような服装に着替えて、人も車もほとんど通らないその道に向かった。遠くに水平線が見え、リーフにぶつかる波の音が聞こえる。浜辺のアダンの木は色鮮やかな緑色をしていて、今日みたいに風のない日は、まるで絵葉書のように少しも動きがない。日は傾きはじめているとは言うものの、南の島の強烈な日差しが刺すように照りつけている。緩やかなカーブが続くその道を、彼はゆっくりと走り出した。それに合わせるように周りの景色もゆっくりと動き出して彼とすれ違っていく。水平線だけがじっとしている。道を横断しようとしていた大きなヤドカリが、気配を感じたのか、サッと宿の中に身を隠した。風がないせいだろう、その音が彼の耳にはっきりと聞こえた。さっきにわか雨が降ったせいで、アスファルトから蒸気が上がるときのあの独特の匂いが漂っている。彼はその匂いだけは那覇の街と変らないことを知って、なぜか少し安心した。でもそのせいで日差しが強烈に反射して、彼の肌に容赦なく熱を伝えてくる。真夏の蒸し暑さが彼を襲った。
2キロぐらい走ったところで、彼の身体からは大量の汗が噴き出してきた。海風に当たりながらのジョギングはとても気持ちいいに違いないと、走りだす前はそう思っていたのに、いざこうして走ってみると、彼はまったくそんな風には感じられなかった。酸素を欲しがって呼吸が速くなっていく身体は、やがて規則正しいテンポに落ち着いたかと思うと、その単調なリズムを感じる以外にはもう何もしたくないというように、ただ坦々と足を前に出しているだけだった。それでも足取りだけは少年らしい軽やかなものではあった。
しばらく走っていると、道の脇にある大きなデイゴの木の下に、4、5人のおばあたちが座っているのが見えた。畑仕事の休憩時間なのだろうか、手ぬぐいを頬っ被りして湯飲み茶碗を口に運んでいる。息を切らしながら彼は、ゆっくりとしたスピードでそこに近づいて行った。するとそのおばあたちが一斉に彼のほうを向いて何やらひそひそと話を始めた。彼は少しバツが悪そうに下を向くようにしてそこを通り過ぎようとした。と、そのとき、一人のおばあが小走りで彼の方に近寄って来て、何か言いながら片手を差し出してきた。何を言っているのか島の方言のようで彼にはよく聞き取れなかったが、かろうじて最後の言葉だけが理解できた。
「これ食べてがんばって走りなさいねぇ」
「あっ....」
考える余裕を与えないほどの素早さで、彼の手にはいつの間にかソフトボールほどの大きさもあるサーターアンダギーが握られていた。うまく状況がつかめないまま、片手にそれを持って彼はどんどんその場を離れていく。あっという間の出来事だった。そのおばあの動きは、とっさの反射神経のような俊敏さがあったのに、それを感じさせないぐらい自然だった。さもそのために準備して彼を待っていたかのような、流れるような身のこなしだった。その場から離れて行くにつれて、不思議な気持ちがどんどん増していく。このサーターアンダギーをいったいどうしたらいいものか、走りながら彼はまったく判断がつかなかった。どう考えてもそれは、ジョギングの人に差し入れられるべきものではないように思えた。それを持って走る自分自身に微妙な違和感を覚えながら、彼は、確かにみずみずしい食べ物とはほど遠い感触を手のひらに感じていた。今自分の身体の中の水分という水分がほとんど汗に持っていかれて、唾液のほうにはまったくその配分が回ってこないというのに、飲み物なしでこれを口の中に入れたとしたら...。想像するだけでそれは軽い拷問のようにも思えた。自動販売機で水やお茶を買うお金など持っているはずがないし(というか自動販売機自体ないし)、かと言ってひと様からいただいた物を捨てることもできない。どうすることもできないまま、彼は、聖火ランナーがゴール地点の陸上競技場に入って行くように、サーターアンダギーを持ちながら集落内に入って行った。
すると、通りの先にあるガジュマルの木の枝に見え隠れしながら、遠くの方から一人の女の子が歩いて来るのが見えた。目を細めるようにしてよく見ると、同じクラスの女の子だ。彼はその子とまだ会話を交わしたことがなかった。集落内ですれ違うのも今日が初めてだ。普段から集落内に人が住んでいるとは思えないほどひっそりとしたこの通りには、当たり前のように歩いている人など一人も見当たらない。このまま行くと二人だけですれ違うことになる。少年は少し胸がドキドキした。実は転校して来て以来一番気になっている女の子だった。
ところがこのとき彼は、ふと自分の外見を意識して、急にいわれもなく恥ずかしい気持ちになった。ジョギングの格好をした自分が、巨大なサーターアンダギーを一個だけ持って走る姿が、なぜかとても不自然で間抜けな人間のように思えてしまったのだ。彼は思わず立ち止まった。ふと彼女の方を見ると、全然違う方を向いていてどうやら彼にはまだ気が付いていない。今ならまだ間に合うかもしれないと、突然体の向きを変えて引き返しかけたが、今この瞬間を彼女に見られていたかもしれないと思うと居ても立ってもいられなくなって、すぐにまた向き直った。それだけで挙動は十分に怪しい。彼女はゆっくりと近づいてくる。通りの脇にある石垣のすき間に一時的にサーターアンダギーをはめ込んでみようとしたが、それはできなかった。そのアンダギーは大きすぎた。ジャージの半ズボンのポケットに入れてみた。太ももにフィットしたズボンの股間のあたりが大きく膨らんだ。会話さえ交わしたことのない女の子とすれ違うのに、こんなに股間を膨らませていいはずがない。すぐにポケットから取り出した。彼女との距離はどんどん縮まっていく。たかがサーターアンダギーを一個もらったというだけなのに、彼の慌てふためきぶりは異常とも言えるものだった。彼は、いまだ経験したことのない状況ゆえに混乱した。たとえて言うなら、ゴルフ場の芝生の上をボウリングの玉を持って歩いている人と同じような印象を、自分に感じていた。この人はたまたまある人からボウリングの玉を受け取っただけなのに、自分がゴルフの格好をしているのと、場所がゴルフ場というだけの理由で、すれ違う人には奇妙な印象を与えてしまう。それと同じような不自然さを感じているのだ。彼女との距離はどんどん縮まっていく。切迫感と焦燥感が彼を襲った。
もっともとりたくなかった行動をとる場面というのは、えてしてそういう時なのかもしれない。彼は、突然サーターアンダギーを口に入れた。その動きは不意をついたように素速いものだった。まるで自動販売機のボタンを押したらすぐに飲み物が下に落ちてくるみたいに、自動的な動作にも見えた。お月さんで言うなら満月から三日月に欠けるぐらいまで一気に噛りついた。そして無理矢理それを飲み込もうとした。手のひらに残ったサーターアンダギーが、もうそれとは判らないぐらいにまで小さくなっている。思っていたとおり、その食感は日にちの経ったドーナツのように、パサパサだった。きな粉を思いっきり口に含んだような食感。わずかに黒糖の香りがしたと思ったその瞬間、口の中の壁という壁にサーターアンダギーが接着剤のようにくっ付いて、喉の途中まで入りかけたそれを吐き出すことも飲み込むこともできなくなった。
(水、水がほしい...)
何か言おうとすると、「パフパフ」というかすかな音だけが聞こえた。
今、救いの道は鼻の穴だけにあった。しかし、炎天下をここまで走って来たせいで、身体の中に十分な酸素を取り入れるためには、ただでさえ鼻の穴だけでは不十分だった。その事実を、こういう状況になって初めて、頭より先に身体が認識した。やばい、苦しい!息が出来ない。彼は悶えた。
すると、向こうから歩いてきた彼女が急に早足になって彼に近づいて来た。ふらついている彼を見てあきらかに様子がおかしいと感じとったのだろう、不思議そうな顔をしながら走り寄って来た。少年と少女は初めて、このような状況で至近距離で目と目が合った。彼女の目の前には、リスのように頬張った少年が立っている。欠けたサーターアンダギーの破片を持ちながら、青白い顔で苦しそうに何かを訴えている。
「どうしたの?大丈夫?」
それは初めて聞く彼女の声に違いなかった。しかし彼の耳にはそれが届かなかった。聞こえているのに、聞こえているという実感がなかった。息苦しい以外は何も感じない。空を仰ぎ見るようにして身体がよろけた。彼の視界は急速に狭くなって、ボウリング玉ぐらいの大きさになり、彼女の白いスニーカーだけがその視界にスッポリ入ったかと思うと、地面に片ひざをついたような感覚から、ふわっとした気分になって、ピンポン玉ほどの空が見えたと思った瞬間、パチンと消えて、真っ暗になった。
「だれかぁ~」
遠くで彼女の声がかすかに聞こえたような気がした。
「あの時はどうなるかと思ったわ」
「オレもね」
学校の帰り道、ちょうど一ヶ月前に彼が倒れたその現場を通り過ぎながら、二人は、ここを通れば必ずあの場面を思い出すというように、笑いながら同じ言葉を口にした。彼女が大声で助けを呼んでくれたおかげで、近所の人たちが何ごとかと表にとび出してきた。目の前に倒れている少年を見た一人のおばあが、素早い動きで彼の口に人差し指を突っ込んだかと思うと、遺跡でも発掘するような手さばきで粉々に砕けたサーターアンダギーをかき出していった。そのあとすぐに別のおばあが水の入ったやかんの口を彼の口に押し込みながら水を注ぎ込み、 パンッ!パンッ!と背中を強く叩いた。このような連携した動きは、かつて何度も経験済みであるかのような、あるいはそのような救助訓練でも行ったことがあるかのような、見事なものだった。背中を叩くその手のひらは、きっと今までに何千個というサーターアンダギーを握ってきた手に違いない。そんな老婆の手のひらが、こんなことで死んだら許さんよとでもいうように、少年の薄い背中に、年輪の重みを含んだ渇を入れていた。彼は咳き込みながら、10粒ほどのサーターアンダギーの破片を噴水のように吐き出すと、大きく喉を鳴らして息を吸い込んだ。背中を叩いた方のおばあが『ハイ、一丁上がり!』とでも言うように、まるで予定していた作業を一つ終わらせた後みたいに、表情一つ変えずにサッと立ち上がった。
「サーターアンダギーは、こんなにしていっぺんに口に入れるもんじゃないよ」
諭すように言うと、おばあは少しだけ笑みを浮かべながら自分の家の庭に入って行った。
「ホントに死ぬかと思ったよ」
少年はあの日以来、だいたいこうして彼女と一緒に帰ることが多くなった。あんなことがなければこんな風に彼女と近づくこともできなかったかもしれないと思うと、サーターアンダギーをくれたあのおばあにも少しは感謝しないといけないのかな、と、なんとなく考えなくもない。
(いや、でもそれはどうかな...)
彼は、しばらくの間はジョギングをする気にはなれなかったが、サーターアンダギーを嫌いになる気もしなかった。