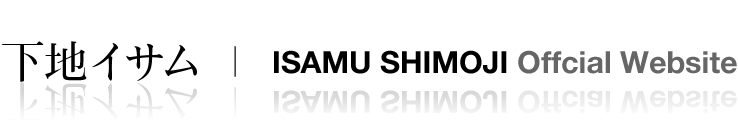旅の最後に...その4(最終章)
「ここでは対応できないわ」
と言ったその女性スタッフは、次のカスタマーサービスカウンターの場所を教える前に、きっぱりとこう言った。
「あなたたち今日はもう飛行機に乗れないわ。詳しいことはそこのカウンターで聞いてちょうだい。ここをまっすぐ行って左に曲がると荷物の受け取り場所があるから、そこをスルーして出口を出たら、エスカレーターで上の階に上がってね。そしたらチェックインカウンターの隣にそのカウンターがあるわ。」
あの猛ダッシュから3時間が経過しようとしていた。
ここで猛然と反論したところで、何一つ進展はないだろう。またそんな気力も残っていなかった。
僕と上江洲さんは、今日マドリードを発つことが絶望的だと知らされたショックで、一気に疲れが押し寄せていた。何をどういう順番で片付けていったらいいかまったく頭の中が整理できない。また、次なるカスタマーサービスカウンターでいったいどんな展開が僕らを待ち受けているのか、明日には間違いなく日本に帰れるのだろうか、考えるだけで鳩尾部分がどんよりと重たくなる感じがした。
「勇、どうやらこのターミナルで寝泊りしないといけないみたいだな」
諦めとも開き直りともつかない声で上江洲さんが言った。
「そうするしかなさそうですね」
僕も途方に暮れるしかなかった。
あのグラナダの楽しかった日々。おいしかったバルのセルベッサ(ビール)。萬徳さんと太郎は今ごろアムステルダム行きの飛行機に悠々と乗り込んでいることだろう。昨日までの、いや、つい何時間前までの滞りない幸せな日々を思い浮かべながら、帰り道のたった一つのスケジュールの狂いが、全てを狂わせ、まさかここまで僕らを疲れさせることになろうとはと、今更ながら思うのだった。
ともすると、今回の旅そのものが悪い印象のまま終わってしまうのではないだろうか。そんな嫌なことが頭をよぎっては、いや、絶対にそうなってはいけない、それは間違っていると、また思い直したりして、トボトボと次なるカスタマーサービスカウンターへ歩いて行くのだった。ここで慌てたところでどうなるわけもないという風に。
案内されたカスタマーサービスカウンターに到着すると、6人ぐらいの人が列を作っていた。僕らは列に並んで静かに順番を待った。程なくして僕らの番が回ってきたので、カウンターの女性スタッフにチケットを見せながらこれまでの経緯を説明すると、
「ああ、それならここじゃありません。向こうのカスタマー・サービスに行ってください」
キターっ!
やっぱりきたよ。
いったいいくつあるのかカスタマーサービスカウンターってのが。「カスタマー」の意味を辞書で引いたら「たらい回し」と書いてあるんじゃないだろうか。もう怒る元気もなかったが、ここで一つだけ言わないと気がすまなかった。
「セニョリータ!決着がつくカウンターだけを教えてくれ」
「ええ、そこで決着がつくわ」
眉毛一つ動かさず、彼女は言い放った。
もう、口に出すのも悔しすぎるその3ヶ所目のカスタマー・サービス・カウンターに行くと、並んでいる人は誰もいなかった。
二人のスタッフのうち、一人の男性スタッフは接客中だったので、もう一人の空いている女性スタッフの方にチケットを差し出した。
「どうしました?」
機械的なその視線の奥には、挑むような閃光だけがあった。
「この飛行機に乗れなかったんだ」
「どうして乗り遅れたの?」
「あなたの会社の飛行機が遅れたからさ。グラナダからの便がね」
「次の搭乗ゲートまでは行ったの?」
「もちろん、着いたら飛行機はもういなかったよ」
「急いだの?」
「...」
「急いでその場所まで行ったの?なのにどうしてこのカウンターに来るのにこんなに時間がかかっているの?」
眉毛一つ動かさない表情というのは、この航空会社の社員教育なのだろうか。
「OK、説明しよう。これで3度目だけどね。まずグラナダからの飛行機が何時にマドリードに到着したのか、そのパソコンで見ればわかるだろ」
「...」
女性スタッフは無表情でパチパチとキーボードをたたいている。
「次に乗り継ぎの搭乗ゲートを見てくれ」
「...」
「乗り継ぎは十分可能だと言ったのはおたくの航空会社だ。なのに飛行機は大幅に遅れ、乗り継ぎ先の搭乗ゲートまでの距離は普通に歩けば30分はかかる。これで乗り遅れたのは僕らが悪いのかな?おまけにこのカウンターに辿り着くまで、別のカウンターで死ぬほど待たされたんだ。そして出てきた答えが「今日は飛行機に乗れません。このカウンターに行くようにと言われてここにやって来たわけだ。僕らはどうしても日本に帰らなければならない。仕事があるからね。どうすれば帰れるかだけでも教えてほしい。」
せめて英語でここまで捲くし立ててみたかったが、そんな長文が組み立てられるわけも、喋れるわけもなかった。しかし、僕と上江洲さんの表情と途切れ途切れの英単語からただならぬ状況を察したのか、その女性スタッフは少しだけ表情を和らげて言った。
「スィー.わかったわ。じゃあ時間がかかるけど待てる?」
「いつまでも待つよ」
「今ちょっと席をはずすけど、ここで待っていてくださいね」
「えっ??...ああ、
あの~...戻って来るよね?」
「もちろんよ、どうして?」
「あなたを信じています」
そのとき女性スタッフは、はじめて表情を崩してプッと吹き出した。
30分ぐらいかかっただろうか。彼女はちゃんと戻って来てくれた。しかし、そこからまたゴールの見えない長い待機時間が始まった。何がどうなって、いや、何の処理にそこまで時間を要するのかまったくわからない。どうやら日本までの乗り継ぎルートをいくつかのパターンで組んだりしているようだが、何しろまったく説明がないし、ひたすら無言だった。
「そうやって待っている間に荷物でも取ってきたら?」
長い沈黙を破って彼女が言った。
考えてみたら確かに僕らは荷物さえ受け取っていなかった。(でもここで待っててくださいと言ったのはアンタじゃないかね?)
僕の心の声を察知したのか、彼女は矢でも射るような視線で、
「一人が待っていればいいでしょ。その間にもう一人が荷物を取ってこれないの?」
(なるほど!それはナイスアイディア!確かにそうだ。しかしその言い草がやはりカチンとくる)
「どこで荷物を受け取ればいいのかな?」
「下のフロアにロストバッゲージカウンターがあるわ。おそらくそこにあると思うわ。そこで荷物の半券を出してちょうだい。」
上江洲さんをその場に残して、僕は言われたとおり下の階のロストバッゲージカウンターに行った。
カウンターにいたのは男性スタッフだった。
「この荷物がここに来ていますか?」
半券を見せながら言った。
「...」
「ここにあるって言われて来たんですけど」
「ノー、ここにはないよ」
あんたで100人目の客だよとでも言いたげな視線だった。
「ホールの中にもう一度入ってくれ」
「どうやって中に入ればいいですか?」
「入口にいる警備員に事情を説明して入るしかないね」
「OK.サンキュー」
スペイン語ならもしかして丁寧に喋るかもしれないとも思ったが...それはでも人間性の問題だろう。
荷物出しベルトのあるホール出口まで歩き、そこに立っている警備員に半券を見せて、「中に入りたいんですけど」というと、
「ノー」
事情を説明しようとたどたどしい英語で喋り始めたが、
「ノー」
と言われるばかりで、一つも進展を見せる可能性はなかった。
相手の態度にいちいち腹を立てるには、もう十分に免疫ができ過ぎていて、かえって軽く流しすぎる自分にちょっと驚いてしまうほどだった。一筋縄に行かないことを当たり前と思っているかのように。結局、疲れだけがたまった以外には、何一つ収穫もないまま、屈辱のカスタマーサービスカウンターに戻って行った。
無言でパソコン画面を見ていた彼女は、帰ってきた僕の姿を見ると少し顎を上げて、
「バッグはどうしたの?」
と言った。
「無かったよ」
「どうして?」
「こっちが訊きたいよ」
「...」
「荷物ベルトのところで受け取るように言われたけど、中に入れなかったんだ」
彼女は口には出さないが「へぇーそうなの?」というような表情でまたパソコンに向き直った。
この問題が解決してから荷物の問題に向かうほうがいいな。僕と同じ事を彼女も悟ったようだった。
カウンターにもたれかかるようにして、時間だけが過ぎて言った。
「ふぅ~」
やっと終わったというようなため息のあとに、彼女は自分自身にも渇を入れるように大きな声で言った。
「オウライ!明日の朝10時半発のアムステルダム行きに乗って、それから大阪関西空港行きの便に乗り継いで、さらに沖縄まで帰ってもらうわ。このルートが一番ベストよ。いいわね?」
「OK.グラシアス!」
「それから今晩泊まるホテルもこちらで用意させてもらったわ。1階到着ロビーのエントランスを出たら、2番乗り場から○○ホテル行きのシャトルバスが出ているから、それに乗ってホテルまで行ってちょうだい。ディナーも朝食もつけてあるから、忘れずにしっかり食べて疲れをとって、明日のロングトリップに備えるのよ」
(なんとありがたいことだ。この人いい人じゃないか)
「オゥ!ザットゥ・ウドゥ・ビー・グレイト」
目の前がパッと明るくなり、長い一日の中ではじめて救われた気持ちになった。
「それであとは荷物ね。私が一緒に付いていくわ」
サッとその場を立つと、彼女は荷物受け取りホールまで僕らを案内してくれた。下のフロアーに行くエレベーターの中で彼女は僕らに話しかけてきた。
「今日はさぞ頭が痛かったことでしょうね。わかるわ。明日は無事にオキヌに帰れることを祈ってるわ」
「オキナワです」
笑いながら僕が言うと、
「オウ、ソーリー、オキナワ」と言いなおして彼女も笑った。
彼女が首から提げているIDを先ほどの警備員に見せると、何も言わずにその警備員は僕らを中に入れてくれた。
「オーケー、まっすぐ行って突き当たりを左に、さらにまっすぐ行くと正面にうちの会社のバッゲージカウンターがあるから、そこでこの紙を見せるのよ」と言って、スペイン語で説明書きがされた一枚の用紙を僕に手渡してくれた。
「グッドラック!」と笑顔で言った彼女に、僕らは少しだけ胸が熱くなった。
「君のことを忘れないよ。グラシアス」と、上江洲さんが清々しい顔で言った。
晴れ晴れとした気持ちで、最後の荷物を受け取るだけのカウンターに向かって歩きはじめた。
「ビクトリーが近づいてきたな、勇」と、上江洲さんが誇らしげな声で言った。そのカウンターまではけっこう距離があったが、そんなことはもう僕らは少しも気にならなかった。
バッゲージカウンターに到着すると、一人の女性スタッフが立っていた。
先ほど受け取った紙をそのスタッフに見せると、
「ああ、これね...うう~ん」
パソコンのキーボードをパチパチと叩くその女性スタッフの難しそうな表情が、もしかしてまたか?という嫌な予感を呼び起こさせた。
「この荷物はここでは出せないので、反対側のカウンターに行って下さい」
キタキタキターっ!
「来た道をまっすぐ戻って、ちょうど向かい側に同じカウンターがあるから」
「OK.ノープロブレム」
僕らは気にしない。いやもう気にしないようにしていないとやってられない。お客様第一主義の日本の商業社会に慣れすぎた自分たちを呪うしかないと思った。ゴール直前に余計なロスタイムは要らない。解放に向かう精神に、もう少しのわだかまりも残したくないという強固な意志がそこにあった。
「トム・ハンクスの顔が思い浮かんでしまったよ」
歩きながら上江洲さんが言った。
『ターミナル』という映画のことだろう。トム・ハンクス演じる主人公が、空港から出発した直後に母国でクーデターが起こり、パスポートが無効になってしまって入国することも帰国することも許されず、異国のターミナルで9ヶ月も生活し続けるという映画だ。その内容を思い出しただけで、ゾクゾクっと背筋が寒くなった。今の僕らが一番観てはいけない映画だろうと思った。
さっきのカウンターの向かい側というにはあまりに遠い次のカウンターまで、いくつものベルトコンベアを通り過ぎなければならなかった。
もうここが最後のカウンターであってほしい。到着後、祈るような気持ちで用紙と荷物の半券を差し出した。
「OK!今あなた方の荷物を出すように指示を出すわ。20分くらいかかるからあそこのソファーで待っていたちょうだい。荷物は4番か5番のどちらかのベルトから流れてくるから、よく見ていてね」
(あ~よかったぁ。ゴールは確実に近づいている)
荷物が手元に戻ってきてこのターミナルの外に出られるなら、もう何だって我慢できるという気持ちになっていた。
僕らが待っているホール内には、同じように荷物が手元に戻ってこなくて困っているように見える人たちが数人いたが、それ以外はまったく到着客らしい姿は見当たらなかった。かなりの数あるベルトコンベアが、空のままでゆっくりと回っている。
世の中というベルトに乗り遅れたり脱線したりして、誰ひとりそのベルトに乗っていないとしても、世の中というのはそうやって空しく回り続けているものなのかもしれない。僕らはあそこから脱落してしまったんだ。下にポトリと落ちた荷物はたちまち行き場を失って路頭に迷ってしまった。誰かがその荷物をベルトに戻してくれることもなく、同情や救いの感じられない世界で、何もかもが寂寥感とともに滞りながら、一つまたひとつと希望を打ち砕いていった。
今こうして荷物を待っている間にも、たくさんの人たちがこの空港から飛び立ち、たくさんの人たちが到着している。秩序正しく流れるように設計され組み立てられたシステムの中で、脱線しないように上手にやり過ごしていくことこそが、生きていくことなのかもしれないと思った。
「のどが渇いたな、勇」
徹夜明け第一声のような弱々しい声で上江洲さんが言った。
「そうですね」
僕もふと我れに帰ると、死ぬほどのどが渇いていることに気がついた。
「飲み物買ってくるけど何か飲む?」
「コーラが飲みたいです」
「わかった」
遠く離れた場所に自動販売機の灯りが見えた。今そこにあった上江洲さんの大きな背中がだんだんと小さくなっていく。その背中はまるでこの一日に僕らが失ってきた自信と誇りを象徴しているようにも見えた。たった一日でどれだけ慌てふためいただろう。ただあたふたするばかりの自分たち、切羽詰った状況を説明しきれない自分たち、怒りをぶつけきれずに縮こまる自分たち、そんな自分たちの弱々しい自信と誇りが、だんだん小さくなっていくあの背中に重なって、何ともいえず悲しい気持ちになった。
4番と5番のベルトの間にあるソファに腰掛けて、そろそろ出てくるであろう荷物との再会に、なぜか懐かしい家族と再会するような気持ちになっていた。自分を思いやってくれる存在が恋しい。そのスーツケースには洗濯機に入れなければならない汗臭い自分の着汚した衣類しか入っていない。でも、それでもそのスーツケースを開けて自分の衣類を確かめられたらどんなに嬉しいだろうと思った。どの国のどの場所に行っても、ホテルに帰ればそのスーツケースが口を開けて帰りを待っていた。謂わばそれは、この旅で唯一の帰る場所だったのかもしれない。
「いさむぅ~、こっちにあったよぉぉ~」
消えそうなくらい遠い場所から、上江洲さんの声が響いてきた。
「えぇ~ぇぇっっ?」
僕は走り出した。次第にスピードを上げ近づいて行った。カウンターの女性が教えてくれたベルトから一番遠い位置にあるベルトで、僕らの荷物が二つだけ回っているのが見えた。
上江洲さんがそのスーツケースに手を伸ばしベルトから降ろしている。そのとき、自分の荷物だけは自分で降ろしてあげたいという衝動がこみ上げてきたが、間に合わなかった。それでも無事に戻ってきてくれたことはありがたい。取り出した荷物の前で上江洲さんが安堵の表情を浮かべて待っていた。
(ありがとう上江洲さん。でも...ギターがない)
「上江洲さん、僕ギター探してきますね」
「勇、もう慌ててもどうにもならんよ。まずは何か飲もう。販売機ここにしかないし」
「そうですね。飲みましょう」
僕は笑いながら言った。勝利を確信した余裕の笑いに見えたかもしれない。
「勇、コーラがバカ高いぞ」
500mlのペットボトルが560円相当の値段だった。
「ホントですね。一番安いのにしましょうよ」
「このスプライトみたいなのだけが異常に安いな」
「それにしましょう」
グラナダでほぼ使い切った財布の中から、ユーロの小銭をかき集めて自動販売機に投入した。
出てきたそのスプライトのようなペットボトルのふたを回すと、プシュッといった。
(やっぱり炭酸だ!よかった)
ゴクッゴクッと、渇いたのどに一気に流し込んだ。
(うわっ、なんだこれは)
上江洲さんもまったく同じリアクションだった。
「ただの炭酸水じゃないですか」
それはまったく甘みも味もない、ただの炭酸水だった。
「世の中甘くないってことなのかもな」
苦笑いしながら上江洲さんがボソッと言った。その言葉は、普遍性を持って今の僕らの状況を如実に語っているように思えて、自分だけの笑いがいつまでも止まらなかった。
「よし、じゃあ一緒にギターを探そう」
上江洲さんの言葉で僕らは別々の方向に別れて、スーツケースを押しながら、ゆっくりと回り続けている空のベルトをいくつも探して回った。だがどこにもギターらしきものは見当たらない。もう一度カウンターに戻るしかないと思ったそのとき、ふと出口の方を見ると、脇の方にわずか10メートルほどの横一本のベルトが目に入った。その停止した真っ暗なベルトの端っこにポツンとギターケースらしきものが置かれている。
「あれだっ! あったよ上江洲さ~ん」
上江洲さんが出口の方に向かって走って行く。
(あー、これでやっとこのターミナルから出ることができる)
暗がりのベルト上で寂しそうに一人ぼっちでいた僕の相棒を取り上げたとき、長い一日が終わったのだと思った。あの猛ダッシュから6時間が過ぎていた。上江洲さんと無言の握手をガッチリと交わし、出口に向かってゆっくりと歩き出した。
「おいしいですね」
向かい合って座るレストランの二人がけ用のテーブルで、僕と上江洲さんはアルコールを飲む元気もなく、それでも十分に満足できる夕食に舌鼓を打ちながら、今日という日を振り返っては、言葉にできない感慨にふけっていた。航空会社が用意してくれたこの旅一番と思われるゴージャスなホテルに半ば戸惑いながら、宿のランクにまったく追いついていない自分たちの外観や、そこを求めてもいないのにそのようなホテルにチェックインしてしまっている自分たちのことが、傍から見るとかなり滑稽に映るのではないかと思った。
「長い一日だったな」
上江洲さんが噛み締めるように言った。
あれからまだ一日も経っていないのに、まるで遠い過去に思いを馳せるような言い方だった。いろんなシーンが思い浮かぶからこそ、出てくる言葉はこの一言に尽きるという感じがした。
「上江洲さん、実はさっきホテルの部屋でインターネットにつないでみたとき、気になるニュースを目にしたんですけど...」
「なにか?」
「アイスランドの火山噴火の影響で、ドイツの空港は今日から閉鎖しているらしいです。風向きによってはアムステルダムもヤバイみたい...」
と、言ってしまってからやっぱり言わなければよかったと思った。上江洲さんの顔が、グラナダで見たフラメンコダンサーのように、一気に悲哀に満ちて伏し目がちになった。ギタリストでもある上江洲さんにその時ギターを手渡していたなら、一番悲しい楽曲を爪弾いていたに違いない。帰りたい情熱と、それが叶わないかもしれないという失望とが複雑に交じり合ったその顔を、僕は生涯忘れないだろうと思った。その場の空気がどんよりと重たくなったのは、もちろん僕もまったく同じ気持ちだったからだ。
「いや、何も考えないで飛行機に乗りましょう。明日を信じるしかないですよ」
自分自身にも言い聞かせるようにして僕は語気を強めて言った。
席を立って部屋に戻ろうと歩き出したとき、
「勇、明日のシャトルバスの時刻表だけ確認してから部屋に戻ろう」
フロントの方に向き直って歩きながら上江洲さんが言った。
さすが現場の鬼だ。
「そうですね。そうしましょう」と僕は、上江洲さんの後を追いながら言った。
フロントで僕は黙って上江洲さんの誇らしい行動を眺めることにした。
「シャトルバス トゥモーロー タイムスケジュール オーケー?」
そこにいたのは、これまた(何なのあんたたち)と言わんばかりの、するどい視線を投げつける女性スタッフだった。
(彼女はきっと今日嫌なことがあったんだろう)
鞭を振り回すような強い口調で彼女が言った。
「それは今必要なの?バスは15分おきにずっと出ているのになんで?」
「グラシアス」
僕らはただそれしか言わなかった。彼女の威圧的な視線に対抗することができなかった。いや、それをしたからって何の解決にもならないことを今日の経験で悟ってしまったかのように、ただの田舎者がお金持ちの貴婦人に渾身のお願い事をしたのに、ぷいっと無視されてあっけなく門前払いにあったような感じで、さも当然のことのように引き上げてしまった。まったくもって気の弱い無力者どもというしかない。
肩を落としながら僕らは、本当に最後の最後にこのフロントに来てしまったこと、こんな質問をしてしまったことを後悔した。
隣同士の部屋の前まで歩いてきて、
「おやすみなさい、ぐっすり寝ましょうね」
とだけ言ってお互いの部屋に入った。
そして僕は、運命を共にした上江洲さんと那覇空港で別れ、石垣行きの飛行機に乗っていた。やっと帰ってきた那覇空港には1時間もいなかった。
アムステルダムから無事に飛び立った飛行機の中で、11時間一睡もせずにこの旅で起こったことを思い返しては、苦笑いして機内食を食べた。
過ぎてから思えば、本当にただただ笑えることかもしれないと思った。たかが一日の、しかもたった一つの便に乗り遅れたぐらいの出来事を、ここまで大げさに、あたかも人生最大の悲劇のように感じてしまったことを、一人機内で思い出しては噴き出してしまうのだった。生きるということは何なのか、幸せの感情とはいったいどういうものなのか、今回の旅のその失敗の中で、何かしら教えられるものがあったようにも思える。
この石垣の後には、さらに香港や台湾でのライブが待っているのにもかかわらず、何の心配もわいてこないし、もう何があっても怖くないと思えるし、むしろ何かもっと凄いことがあってほしいと思うぐらいの図太い何かが自分に芽生えているのだけは確かだった。
非常に強い台風2号が近づいているため、やむを得ず着陸できない場合は那覇空港に引き返すこともありますという条件付きだったにもかかわらず、無事に飛行機は石垣空港に着陸した。
僕はそのとき心から思った。
(ターミナルは小さいほうがいいな)