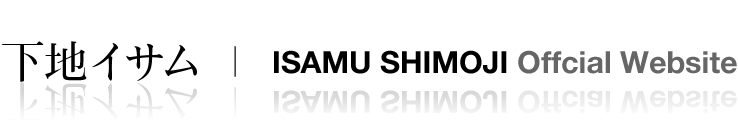ブルース・リーとヤギ
ブルース・リーの話をし出したら、なんかいろんなことを思い出してしまった。
僕は小学生のとき、ブルース・リーが大好きで、部屋に大きなポスターを貼っていた。
上半身裸で、大胸筋に鋭い鉄爪で引っ掻かれた傷を見せ、ヌンチャクを持ってあの独特のかまえをしたポスターだ。
僕はあのポスターが大好きだった。
ブルース・リーの表情というものは、まさにブルース・リーだけが持つ孤高の表情のように思われた。誰にも負けるはずがないという強さの裏に、痛みを与えてしまう相手に対してどこか「ごめんね」みたいな、慈しみの感情を併せ持ったような独特の表情だ。
そう、どことなく物哀しくて切ない。
武道を極めたつわもののみが持つ哀悼の魂の現れなのだろうか。
ブルース・リーは、己のたたずまいとその表情のみで、幼い僕らの心までもパーフェクトに掴んでいた。それは言葉を超えて伝わる美徳のようなものだった。
だから僕はブルース・リーが大好きだった。
「アチャー」と叫びながら、ランニングシャツを脱ぎ捨て、ブルース・リーに少しでも近づこうと、何度もその表情を真似ては身体を揺らしてかまえた。
「アチャー、アチャー」と何度も雄叫びを上げていたので、しまいには隣の部屋にいた兄貴がやって来て、
「うるさいっ!」と怒鳴った。
「やるんならどっか誰もいない場所でやってくれ」
僕は仕方なく階段を下りて一階の一番座といわれる客間で、
ランニングシャツを着ては脱ぎ、「アチャー」と叫んでは構え、またランニングを着ては脱ぎ、これを何度もくり返した。
すると、二番座(居間)でテレビを観ていたおばぁが、
「相撲が聴こえんよ」
と言い出した。
僕は無言で外に出た。寡黙なところも完全になりきっていた。
家の庭でまた同じことをくり返し、スッとかまえると、目の前をパリ帰りの馬車が通って、馬車の上のパリジェンヌおばぁが僕を見てニヤニヤしながら過ぎていくので、恥ずかしくなり、いよいよ行き場がなくなって、僕はタツ(馬小屋)に入った。
馬はおじぃと一緒に畑(パリ)に行っているので、タツには6匹ほどのヤギしかいない。絶好の場所だ。
上半身裸でヤギたちの前まで行き、サッとかまえると、
ヤギたちはビクッとして視線は僕に釘づけになった。
彼らを敵に見立てるように身構えて、ブルース・リーのあのお決まりの甲高い裏声で
「アチャー」と言うと、
「メェェ」と鳴いた。
アチャーと言えばメェー。
アチャー メー。
まるで沖縄民謡のような...
って、そんなことはどうでもいい。
「アチャチャチャチャ アチャアアァァァ~!!」
と大声で叫ぶと、
「メェェェ、メェ、メェェ~」
と、ビクつきながらヤギたちもそれぞれに鳴き返してくる。
そしていよいよクライマックスは、あの切ない視線だ。
ブルース・リーにしか醸しだせない、かすかに悲哀を含んだあの視線を真似て、ヤギたちを一匹ずつなめるように見つめていった。
するとヤギたちは、あのビー玉のようなブルーな瞳で、ヤギたちにしか醸し出せない、世の中の真理を知り尽くしたような、それでいて僕の心の中を見透かしたような眼差しで見つめ返してきた。
睨み合い、いや、見つめ合いは続いた。
首を少し斜めに傾げながら、ヤギたちは少しも動かない。
僕だけがわずかに上半身を揺らしている。
身も心も完全にブルース・リーになっていた。
寂寞(じゃくまく)とした静けさが続いたのち、
ヤギの首がゆっくりとうな垂れるように下を向いたかと思うと、モグモグと草を食べはじめた。
アゴを動かしながら再び僕を見つめる彼らの視線は、興醒めしているようでもあり、おちょくっているようでもあった。
敗北感とともに僕はタツの外に出た。
ランニングシャツが、汗と汚れにまみれ、のびのびになっていた。
どうでもいいことかもしれないが、
その頃の僕は、
ブルース リーのことを
ブルー スリーだと思っていた。
どうでもいいはずがない。
真似事はできても、本人にはなれない。
偉大なブルース・リーよ、ごめんなさい。